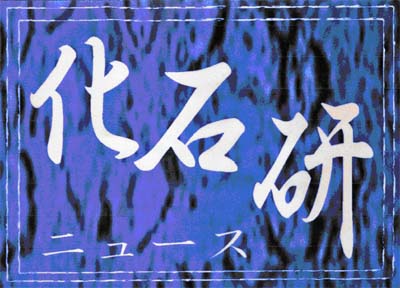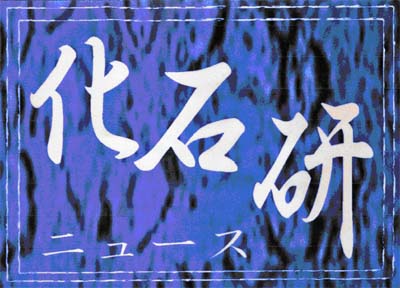第28回(通算133回)総会・学術大会は下記の予定で行われます.ふるってご参加ください.前回に引き続き,自慢の標本,復元模型・復元図,写真,資料などの展示発表も企画しています.
総会議事
一般講演
一般講演,ポスター発表,展示発表を募集
第28回総会・学術大会における一般講演,ポスター発表,展示発表を募集します.次の要領で申し込んでください.
<一般講演、ポスター発表をご希望の方>
[演題申し込み]
締め切り:3月31日
方法:郵送あるいはメールで、講演者名、演題、口演・ポスターの別をお知らせください。
[講演要旨]
締め切り:4月30日
方法:演題、発表者(所属)、要旨をA4版用紙1枚に収まるように記入し(要旨本文は約600字が目安)、メール添付で送付、あるいは完成原稿を郵送してください。
一般講演は10~15分、ポスターボードは縦180cm、幅90cmを予定しています。展示発表、サテライト集会などの申し込みは準備係の笹川一郎へお寄せください。メール添付文書のが場合は、お手数ですが
MS Word 2003 (Win XP) で読める形式にして送ってください( Word 2007 の docx は読めません)。
連絡先;
笹川一郎
日本歯科大学新潟生命歯学部
先端研究センター・解剖学
〒951-8580 新潟市中央区浜浦町1-8
TEL: 025-267-1500, FAX: 025-267-1134(先端研 笹川宛)
E-mail: ichsasgw@ngt.ndu.ac.jp
~ ~ ~ ~ 第132回例会の報告 ~ ~ ~ ~
2009年11月21日(土),22日(日)の二日間にかけて,豊橋市自然史博物館において第132回例会が開催されました.21日には,「古生物の復元」をテーマとした講演が,また,翌22日には「のんほいパーク(豊橋総合動植物公園)」の見学会が行われました.今回の例会には,化石研究会の会員のほか,博物館近隣の地学関係者,豊橋自然史博物館の利用者の方々も加わり61名の参加となり,用意された会場はほぼ満席で,活気ある講演会となりました.
一日目の21日は,神谷会長の挨拶に始まり,4講演が行われました.まず松岡敬二氏による「博物館にみる無脊椎動物の復元」の講演では,豊橋市自然史博物館の常設展示の紹介がされ,展示の工夫の多様さに驚きました.一方で,博物館での復元展示では,学術的な成果と,展示の製作時期・方法及び目的の間でずれが生じてしまうという問題について考えさせられました.
次に,「古植物の復元‐部分から全体像をイメージする展示」という講演が吉川博章氏によって行われました.部分的に産出する植物化石から全体像をイメージするための工夫の話に,大人も子供も楽しめる展示を作るという目標への意気込みを感じました.
午後は,大野照文氏による「謎の生き物エディアカラの化石の復元にチャレンジ」から始まりました.これまでの歴史の中で作られてきた復元モデルの比較や,エディアカラの化石に見られる食い違い相称についての内容に,エディアカラ化石の復元の難しさと面白さを感じました.
最後に田中源吾氏の「例外的に保存された節足動物の眼の化石とその復元」についての講演が行われました.カンブリア紀大爆発のきっかけとなったひとつの仮説である「光スイッチ説(眼の誕生)」を根底に,新たな目線からカンブリア紀大爆発を考える講演は刺激となりました.講演終了後には,豊橋駅近くで懇親会が行われ,和やかな雰囲気の中,親交を深めることが出来たようです.
翌日の「のんほいパーク」の見学会は,園長の齋藤富士雄氏の案内で動物たちや施設の見学が行われました.見学会の最後には,シロサイの体に触らせてもらうという貴重な体験もでき,参加者一同大満足の見学会でした.最後になりましたが,今大会を準備された豊橋市自然史博物館のスタッフの皆様方,ご協力いただいた「のんほいパーク」の方々に厚くお礼申し上げます.
(吉田亜希菜)
 |
 |
| シンポジウムの様子 |
恐る恐る柵ごしにシロサイを触ってみる参加者 |
間島信男のお勧め本の紹介
<教科書・教科書的な本(大学生以上向け)>
1)『これからの進化生態学-生態学と進化学の融合-』Peter Mayhew[著]
江副日出夫・高倉耕一・巌圭介・石原道博[訳]共立出版,262p.(2009年3月)¥4,200円+税.
学部の卒論クラスか院生のテキストとして,発展著しい進化生態学の全体を概観し,その成果と方向性を知るにはよい教科書である.特に後半の種の誕生,種の絶滅,大進化の各章は,古生物専門家にも興味深い章ではないだろうか.(★★★)
2)『動物分類学』 松浦啓一[著]東京大学出版会,139p .(2009年4月)¥2,400円+税.
学部学生向けの動物分類の入門的なテキストである.非常にハンディで分類学のABCが一通りはわかるという点では,著者の意図は十分に果たされているといえよう.ただ,あくまで入門書なので,方法論や研究の実際については,本書の巻末にあげられている教科書でさらに勉強する必要がある.著者の専門が魚類分類学なので,実例が魚類に偏っている点はいたしかたないか.(★★)
3)『古生物学』 速水格[著]東京大学出版会,214p.(2009年9月)¥3,400円+税.
久々に出た本格派の学部学生向け古生物学のテキストである.著者の思想が色濃く反映されているという大学の教科書の見本のような本で,古生物学がどういう学問かわかる.評者はかねてより,通勤通学の途中でも読める読み物ではない本格的な教科書はないかと思っていたが,まさにぴったりの本である.A5判ソフトカバーで厚すぎない.例が軟体動物に偏っているのは,著者の専門上やむを得ないとすべきだろう.(★★★)
<論文集>
4)『ダーウィン『種の起源』の系統樹』現代思想4月臨時増刊号.第37巻5号.310p.(2009年4月)¥1,800円.
巻頭には,『種の起源』刊行の前年にリンネ学会で読み上げられたダーウィンの論文「種が変種を作り出す傾向について,および変種と種が自然による選択によって永続化することについて」の新妻昭夫による訳と解題が掲載されている.その他,対談1編,進化理論から芸術・哲学の分野にいたるまで,進化論が影響を及ぼした各分野からの寄稿17編が収められ,巻末には,佐倉統・三中信宏編による進化論に関する時代別,主題別主要著作ガイドがある.(★★)
5)『周明鎮科学文集』中国科学院古脊椎動物与古人類研究所[編], 周明鎮[著]科学出版社,北京.1071p.(2009年6月)約¥13,000円.
『中国的象化石』で記憶に残る中国の著名な古生物学者周明鎮(1918~1996)の学術論文141編を復刻した論文集で,新生代の古脊椎動物関係の論文が多い.この分野に興味がある人は是非どうぞ.(★★★)
<一般普及書(読み物)>
6)『分子進化のほぼ中立説-偶然と淘汰の進化モデル』太田朋子[著]講談社ブルーバックスB-1637.170p.(2009年5月)¥800円+税.
中立説では,分子レベルの突然変異は自然淘汰に対して中立な変異が多く,遺伝的浮動によって集団中に固定されるとする.しかし,中立説ではうまく説明できない現象もあり,「ほぼ中立説」を考えるとうまく説明できるという.この説は,現在国際的に高く評価されているとのことである.最初に巻末の用語集を読んで,2章,3章を拾い読みして概要を頭に入れてから,第1章に戻ったほうが良いかもしれない. (★★)
7)『チリモン博物誌』きしわだ自然友の会[著]幻戯書房.189p(2009年6月)¥1,600円+税.
チリメンジャコに混じっているカタクチイワシ以外の動物「チリメンモンスター(略してチリモン)」の解説書である.同友の会ホームページではカラーのチリモン図鑑が見られる.チリモン探し専用のチリメンジャコを売っている業者もある.化石を主題としていないが,海の生物多様性を知るには絶好の教材である.はまると怖い.(★★★)
8)『大絶滅- 2億5千万年前,終末寸前まで追いつめられた地球生命の物語』.Erwin[著],大野照文[監訳],沼波信一・田昌宏日[訳]共立出版.323p.(2009年6月)¥3,500
円+税.
白亜紀末の絶滅に関する本は多いが,ペルム紀末の絶滅をテーマにした本は初めてではないだろうか.著者はこのテーマを専門に研究してきた人で,自身の研究も踏まえながら諸説を丹念に分析・紹介している.(★★)
9)『太古の光景-先史世界の初期絵画表現』マーティン・J. S.ラドウィック[著]菅谷暁[訳]新評論.284p.(2009年7月)¥4,500円+税.
著者は古生物学史が専門で,『化石の意味』(1972)などがある.原書は1992年に出版された.1700年代から1800年代に描かれた先史時代の復元画を並べ詳しい解説を述べ,化石がノアの大洪水の証拠となっていた時代から,近代地質学の黎明期にいたるまで,いかに復元画というジャンルが確立されていったかを論考している.(★★)
10)『チャールズ・ダーウィンの生涯-進化論を生んだジェントルマンの社会』松永俊男[著]朝日新聞出版,朝日選書857.321+ⅹp.(2009年8月)¥1,400円+税.
最新の資料研究に基礎を置き,正確な事実に基づくダーウィンの伝記を展開している点に特徴がある.「日本だけに広がっているダーウィン神話に注意」し,その誤りを指摘するとの方針はよく貫かれている.文章は簡潔で読みやすく,分量も手頃である.今後,ダーウィンの伝記の定番となる本であろう.(★★★)
11)『ザ・リンク-ヒトとサルをつなぐ最古の生物の発見』コリン・タッジ[著]柴田裕之[訳]早川書房.382p.(2009年9月)¥1,800円+税.
ドイツの有名な化石ラガシュテッテンのメッセル頁岩から発見された保存完全の霊長類化石の発見物語とその進化上の意義について解説している.果たして“イーダ”は我々の祖先なのか.(★★)
12)『種の起源』チャールズ・ダーウィン[著],渡辺政隆[訳]光文社古典新訳文庫.上巻 423p.(2009年9月)¥838円+税.下巻 436p.(2009年12月)¥838円+税.
初版の新訳である.読みやすさを基本としているので,岩波文庫の八杉訳とは異なり,注釈はなく,上下2巻本である.訳者はグールドのエッセイなどの翻訳を多く手がけている人で,上下巻ともに同人による読者のための解説が付いている.(★★★)
一般普及書(ビジュアル中心)>
13)『アンモナイト-アンモナイト化石最新図鑑 蘇る太古からの秘宝』ニールL.ラースン[著],棚部一成[監訳]坂井勝[訳]アンモライト研究所.256p.(2009年10月)¥3,400
円+税.
世界各地のアンモナイト化石を美しいカラー写真で解説.英文と和文が併記されている.アンモナイトのガイドブックとしては手頃だが,著者と発行所の関係からか,化石販売業者のカタログ風な感じが本全体から漂ってくる.(★★)
14)『世界の化石遺産-化石生態系の進化』P.A.セルデン・J.R.ナッズ[著]鎮西清高[訳]朝倉書店.(2009年11月)¥4,900円+税.
エディアカラ丘陵からランチョ・ラ・ブレアまで,世界14の例外的に保存がよい化石産地(化石ラガシュテッテン)を豊富なカラー図版を使って解説した本で,原著は“Evolution of Fossil Ecosystems“(2004).生態系の変遷を解説しているのではなく,各産地の紹介が主題である.(★★★)
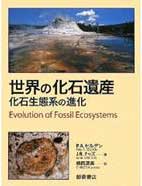
事務局だより
■ 50周年記念事業のための募金のお願い
50周年記念総会とそれに続く出版などの記念事業の実施を財政的に援助するため,会員の皆様に醵金をお願いいたします.
金 額 1口2000円とし,何口でも可とします(端数でも結構です).
方 法 このニュースに同封の郵便振替用紙により,郵便局(ゆうちょ銀行)から化石研究会の郵便振替口座に入金してください(振込料金無料).
口座番号:00910-5-247262,加入者名:化石研究会.
(会費の納入と区別できるよう,50周年募金と明記してください.)
最終締切 2010月末日
【現在までに募金を戴いた方々】
堀口萬吉・金 光男・大石 朗・髙野武男・吉田唯義・小幡喜一・浅見昭子・北林栄一・長谷川美行・三島弘幸・篠原 暁・野村正純・吉羽興一・寒河江登士朗・秋山雅彦
・根本直樹・後藤仁敏・小林昭二・石田吉明・佐藤智子・吉田 尚・田崎和江・鈴木秀史・ 糸魚川淳二・石井久夫・島口 天・近藤洋一・藤本艶彦・木村方一・岡村喜明・加藤正明・ 宮崎重雄・北川博道・柴田松太郎・笹川一郎・谷戸 茂・平井明夫・仲谷英夫・中井 均・岩月信一・筧 光夫・吉川義雄・赤木三郎・星見清晴・真野勝友・犬塚則久・小林健助・田中里志・間島信男・高桑祐司・広田昌昭・福嶋 徹・楡井 尊・高橋啓一・神谷英利・ 大森昌衛・白井浩子・古沢 仁・松岡敬二・島本昌憲・徳永重元・大澤 進・小林巌雄・高橋正志・品田やよい・柴 正博・千代田厚史・堀田信子・杉田正男・小西省吾・橋屋 功
以上71人 合計 510,090円
■50周年記念に関連する写真や情報の提供
50周年記念事業で使用する化石研の歴史に関する写真や資料,情報を集めています.お持ちの方は事務局までご一報ください.祝賀会,出版物,ホームページなどで使用させていただきます.
■新入会員 松本みどり(千葉大学), 蔡 政修(台湾国立自然科学博物館),
■2010年度会費の納入をお願いします
年会費 4000円(学生2500円)
郵便振替 00910-5-247262 「化石研究会」
* 3年間会費未納の会員は,除籍となりますのでご注意ください
.