|
2002年1月15日発行
第20回・化石研究会総会・学術大会のご案内
第20回化石研究会総会・学術大会(2002年・通算117回)を、下記のように大阪市立自然史博物館で開催することが決まりました。ふるっての参加と研究発表の申し込みをお願い申しあげます。
★期日 : 2002年 7月6日(土)・7日(日)
★会場 : 大阪市立自然史博物館
★一般研究発表申し込み 締切り 4月30日(厳守)
研究発表には、口頭発表とポスター発表の両者があります。口頭発表にはスライド・プロジェクター、オーバーヘッド・プロジェクター、パソコン用液晶プロジェクターを用意します。ポスター発表には、横90?、縦160?のスペースを予定しています。
研究発表申し込み方法
発表者氏名(複数の場合は口演者を筆頭にし、○印を付ける)、所属、演題名、口頭発表かポスター発表の選択、連絡先(氏名、住所、電話、Eメール)を明記して、下記・大阪市立自然史博物館の石井久夫会員まで、郵送、FAX、Eメールのいずれかで、4月30日(必着)までにお送りください。
要旨原稿(締切り6月15日) この原稿は後日、会誌に掲載されます。
研究発表要旨の原稿を6月15日(土)までに、下記へお送りください。原稿は、パソコン使用の場合、A4紙にフォントサイズ12で、本文は1行38字×13行、上段に演題名、発表者氏名、所属を入れ、できるだけEメールで送付してください。郵送の場合はフロッピーとハードコピーをあわせてお送りください。むろん手書き原稿も可。
送り先:石井久夫 大阪市立自然史博物館 〒546-0034大阪市東住吉区長居公園1-23 電話06-6697-6221 FAX06-6697-6225
●プログラム発送:5月15日の予定
★日程(内容変更の場合もあります)
7月6日(土)午前:運営委員会、午後:特別講演・一般講演・総会、懇親会
7月 7日(日)午前:一般講演、午後:一般講演・館内特別展と収蔵庫の見学
★世話人代表:石井久夫★参加費:500円(資料代を含む)
化石研究会運営委員会の概要記録
定例運営委員会が2001年12月15日(土)午後2時から筑波大学学校教育部で開催されました。以下のその概要を掲げます。
●報告事項としては事務局および編集委員会から最近の運営に関わる事項として、事務局の運営状況、会誌の編集状況、会計、他の団体との共催行事などについて各担当者から報告があった。
また、新潟からの事務局移転にともなう郵便振替貯金口座の変更、新しい封筒の印刷等が行われた。
●議題
(1)新しい入会者1名、退会希望者3名を承認した。
(2)2002年度およびそれ以降の総会・例会・諸活動について。
2002年度総会・学術講演会は大阪市立自然史博物館の会員諸氏のご協力を得て、2002年7月6日(土)から7日(日)の2日間、大阪市立自然史博物館(大阪市東住吉区)で開催することとなった。現在、特別講演の講師を依頼中である。
また、秋(あるいは夏?)の例会は琉球大学(沖縄県)の伊佐英信会員を中心に計画していただくことになった。この場合、準備のための人的援助が必要とのことである。さらに、2003年以降の予定についても具体的な開催地候補が挙げられて議論がされた(金沢大学、兵庫県立人と自然の博物館ほか)。
(3)「古生物学的進化論」の出版について。
後藤仁敏会員から前の総会以降の経過について説明があり、化石研究会として同書を出版することを了承した。なお、出版形態は会誌特別号とせず、化石研双書という新しい出版物の形態とし、その扱いは双書委員会が行うこととした。
(4)事務局移転にともなう会誌、交換雑誌、蔵書の移転について。
具体的な候補が挙げられ、新潟から移送することとした。
(5)会則変更をともなう会の運営についての提案について。
会員有志から提案された研究会名称の変更を含めた会則の改正案について、主旨説明を受け質疑応答を行った。今後さらに多くの会員の意見を求めつつ、議論を継続することとした。
以上が概要です。詳細については公式議事録(事務局)にあります。 (神谷英利)
化石研双書 創刊
(化石研究会会長 真野勝友)
2頁に掲載されているとおり、化石研双書1号が刊行されました。以下は、化石研双書・創刊にあたっての化石研究会会長の創刊のことばです。
化石研究会では、化石研究のための入門、進化論や化石研究の一般論、データ集、技術論・方法論、環境と古生物、古生物学の普及など、古生物学に関する重要な問題をテーマとした「化石研双書」を刊行することを決定しました。
これまで「化石研究会会誌」に掲載された論文などを掘り起こしたり、オリジナルな原稿を書いていただいたりして、古生物学に関する古くて新しい課題を今日的視点で展開していただくことを期待します。
化石研双書1号
井尻正二著『古生物学的進化論の体系(要旨)』の刊行について
1988年から1992年まで本会で行なった勉強会での故井尻正二会員の報告をもとに残された遺稿『古生物学的進化論の体系(要旨)』は、12月15日の運営委員会で化石研双書1号として発行されることが決定されました。内容は、化石研究会会誌に6回にわたって連載された井尻会員の報告を中心に、井尻会員の新しい遺稿、文献、資料などを追加したものです。
私ども双書委員会では、化石研双書1号の出版について、運営委員会の決定にもとづいて、実務を進めてきました。その後の作業としては、提案者である真野会長名の「化石研双書創刊のことば」を表紙2に入れ、表紙のデザインを考案したうえで印刷に入れました。
双書1号は、1月中旬には出版されることになりました。双書の体裁等は今回は暫定的に私ども委員会で考えましたが,今後更に会員の皆さんのご意見を募って決めていきたいと思います.なお,双書は会誌と違ってその性格上希望者のみに配布されることが運営委員会で決定されております.したがって,全会員には配付されないものです。しかし,今回は、ご遺族のご希望とご厚意により全会員に発送することになりました。印刷され次第、会員の皆様に発送いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。
なお、発送、印刷所からの経費請求、遺族への報告と支払い等に関する相談等、なお当委員会と事務局とで連絡を取りながら処置すべき点が残されております。このうち発送に関しては運営委員会での折り、後藤と事務局の三島の間で取り交わした合意により、当委員会で行いますが、その他については、今後協議の上、逐次ご報告いたしますので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。
2002年1月11日 化石研双書委員会・真野勝友・後藤仁敏
【講演会のお知らせ】
舒 徳干 教授、最新の成果を語る
カンブリア爆発における新発見
講演者:舒 徳干 ShuDega教授 中国西北大学教授、生命の海科学館名誉館長
主催:生命の海科学館
講演は中国語ですが日本語の同時通訳があります。
日時:2002年 2月2日(土)午後1時30分から
2月3日(日)午後1時30分から
会場:蒲郡情報ネットワークセンター/生命の海科
学館1Fメディアホール
応募方法:平成14年1月15日(火)から、電話、ファックス、またはe-mailで参加申込を受け付けます。
定員 各先着60名、ご希望の日付けをお知らせください。
両日とも内容は同じです。申込み、お問い合わせ先:蒲郡情報ネットワークセンター/生命の海科学館
〒443ー0034 愛知県蒲郡市港町17ー17 電話0533ー66ー1717、ファックス0533ー66ー1817、
※参加は無料です。
▼中国雲南省の澄江(チェンジアン)は今からおよそ5億3000万年前のカンブリア紀の多様な動物たちの化石が発見されることで有名です。なかでも舒教授たちが発見した最古の脊索動物の化石は世界中から注目を集めています。私たち人間を含む脊索動物の祖先がどのような過程をへて進化してきたのか、その謎はまだ解かれていません。この一年に舒教授が進めてきた研究はその謎をとく手がかりにもっとも近づいていると言えるでしょう。英国科学雑誌『ネイチャー』にも発表されました。 (講演案内パンフレットより)
【図書案内】
恐竜の世界をもとめて
デボラ・キャバトリー著、北代晋一訳
無名舎、本体2600円
"The Dinosaur Hunters: A True Story of Scientific Rivalry and the
Discovery of the Prehistoric World"の全訳である。著者は『メス化する自然』(集英社)で知られるイギリスのBBC放送の科学担当プロデューサーである。
19世紀のイギリスにおける恐竜の発見者たちの物語である。紹介されているのは、まず、イクチオサウルスやプレシオサウルスの発見者であるライム・リージスの貧しい化石売りであったメアリー・アニングである。読者は、学歴もない彼女が、偉大な発見をするために化石をさがす姿に強く胸を打たれるだろう。彼女の業績は、彼女の発見した化石とともに、ロンドンの自然史博物館で紹介されている。
つぎに、オックスフォード大学教授の地質学者、ウィリアム・バックランドである。史上最初の恐竜・メガロサウルスを記載するが、聖書と進化論の矛盾に苦しみ、ついには精神錯乱を陥ってしまう。
3番目が、貧しい医師であったギデオン・マンテルである。開業医と古生物学者の二足の草鞋をはいた彼は、イグアノドンとヒラエオサウルスの記載をするが、晩年は家庭の不幸、オーウェンとの確執に苦しみ、馬車事故の後遺症から無念の死を遂げる。貧しい患者におしみなく医療を施しながらも、恐竜研究にささげた彼の情熱に多くの読者は感動するに違いない。ロンドン自然史博物館では、彼の業績はしっかり展示されている。
最後に紹介されるのは、解剖学者のリチャード・オーウェンである。若き才能に恵まれた解剖学者として登場するが、イグアノドンの復元を誤り、ダーウィンによって唱えられた進化論に反対するなど、みじめな晩年を送ったとされている。彼の銅像はロンドン自然史博物館の1階の奥に、初代館長として立っている。
とくに、驚かされたのは、オーウェンがマンテルとの確執の中で、みにくい陰謀家として描かれていることだ。"Odontography"や"On
the Anatomy of Vertebrates"の著書で知られる彼が、そんな人間だったとは、信じられない思いがした。おそらく、著者がマンテルにあまりに同情し過ぎたために、オーウェンを悪者にしてしまったのだろう。
評者は昨年の夏、ロンドン自然史博物館でこれらの人びとの業績を目の当たりにしてきただけに、臨場感あふれる思いで、興奮して一気に読んでしまった。また、評者が故井尻正二氏と書いた最初の本のタイトルが本書に似た『恐竜の世界をたずねて』(千代田書房、築地書館)であったことにも深い因縁を感じる。恐竜に興
味ある会員諸氏に是非ともお勧めしたい本である。 (後藤仁敏)
ヒトのかたち5億年
犬塚則久 著
てらぺい(2001-04刊)
A4判 64頁 2400円+税
本書は、ヒトのからだを中心にした脊椎動物の比較解剖学の入門書である。からだの素朴な疑問、たとえばなぜ口の上に鼻があるのか、といった問題がつぎつぎに解き明かされている。からだの中でも、体表から見当がつくような構造を中心に話題が進められており、とても親しみやすくなっていて、教材としても優れていよう。
著者がもっとも得意とする手足や背骨の骨格や筋肉系については、用語や表現に難解さがあるものの、さすがに他書にないユニークな解釈が展開されていて面白い。目次の項目もまたユニークで、たとえば人体部品年表のほか、首、肩、ひじ、腰、股、こめかみ、唇、尻、などとつづく。
たぶん本書の最大の特徴は図にある。各項目が見開の2頁の中にまとめられていて、その左頁に文章が配列され、右頁は全面が図になっている。図はいくつかの写真のほかは、すべて著者のオリジナルの図から構成されている。その図がユニークで、図のもとになったのが、著者が講義の際に黒板にチョークで描いた絵だそうだ。これをもとに水彩色鉛筆などを使って水墨画風の絵に仕上げている。絵は簡潔で、よく要点が表現されておりとても感心する。
一方、この本の欠点は表紙の装丁にある。配色もデザインも悪いが、なによりも絵がよくない。あとがきによると、この絵だけが著者の作ではないらしい。惜しまれる。 (小寺春人)
現代進化学入門
C.パターソン著、馬渡峻輔・上原真澄・磯野直秀訳
岩波書店 2001年9月発行
283頁3800円+税
本書は題名が示すように進化学の入門書であり、総説的に平易に書かれている。現代進化学の到達点を広く知りたい方に最適である。したがって、個々のテーマについて深く知りたい方には不向きである。とはいえ、内容のレベルは高い。
本書はColin Patterson著、Evolution, Second Edition, The Natural History
Museum, London, 1999 の翻訳で、初版は1978年に発行され、これも好評を得て翻訳されている(磯野直秀・磯野裕子訳、現代の進化論、岩波書店、1982)。
著者はロンドンの自然史博物館古生物学部門に在籍した著名な魚類、特に全頭類化石研究者である。93年に博物館を退職され、98年3月に本書の最終原稿を余人に手渡した3日後に亡くなっている。
著者は化石魚類についてのおおくの研究成果を残している古生物学者である。しかし、本書で化石について触れてあるのはわずか8頁ほどである。化石研究者はこれをどう受けとめたらよいのか。物足りない、と思うか。私はむしろ、広い進化学の観点からの化石資料、古生物学的進化論の位置づけの議論が今私たちに希薄となっているように感じた。特に、個別分野に埋没した研究生活を送っている方、よぎなくされている方に一読をお勧めする次第である。 (笹川一郎)
Human Osteology. 2版
D. White著, P. A. Folkens描画,
Academic Press, 2000-01, 563p,
\29216.
Development Juvenile Osteology
L. Scheuer, S. Black著, A. Christie描画,
Academic Press, 2000-08, 587p,
\21074.
The Origin and Early Diversification of Land Plants.: A Cladistic Study.
P. Kenrick, P. R. Crane著,
Smithsonian Institution Press, 1997-08, 592p
\3946.
Mesozoic Vertebrate Life
D. H. Tanke編,
Indiana University Press, 2001-06, 352p,
\6581..
白亜紀に夜がくる─恐竜の絶滅と現代地質学─
JLパウエル著、瀬戸口烈司訳、青土社、
\2800.
恐竜が動きだす─デジタル古生物学入門
笹沢教一著、中公新書ラクレ、
\660.
痛快!恐竜学
平山 廉著、集英社インターナショナル、
\1700.
【会員動向】
逝去された会員 2名
退会者 3名
新入会員 1名
会員数(2001年度12月現在) 会員数:249人
原稿募集
化石研ニュースへの原稿をお寄せください。国際学会情報、国内学会情報、研究紹介、論、文紹介、化石発見情報、「会員の声」、「化石研究の道具」、「書籍紹介」、「ひとつの化石」(次号から掲載の予定で、会員のもっとも印象に残った化石のエピソード)など。宛先(小寺)は、下記を参照ください。
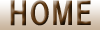
|

